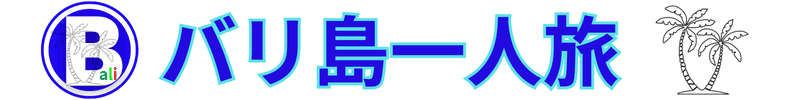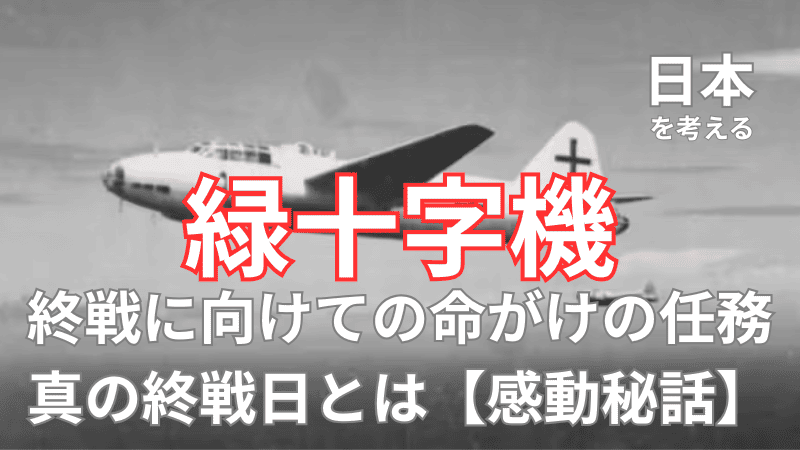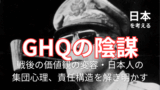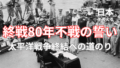1945年8月15日正午。ラジオから流れた天皇の声を、日本中の人々が固唾をのんで聞き入りました。
「耐えがたきを耐え…」——それはポツダム宣言受諾を告げる、歴史的な放送でした。多くの国民が「これで戦争は終わった」と思ったでしょう。
しかし、現実はそう単純ではありませんでした。
玉音放送は「降伏の意思」を表明しただけで、正式な降伏文書の調印や占領軍の進駐、武装解除が終わるまでは、国際的にはまだ戦争状態。
しかも国内には「徹底抗戦」を唱える軍人たちが存在し、厚木航空隊は玉音放送直後に“部隊独立宣言”を出して再び立ち上がろうとしていました。
一方、北方ではソ連が終戦宣言を無視して侵攻を続け、北海道の一部を占領する計画まで持ちかけていたのです。
この緊迫した情勢の中、米軍は日本に対し、降伏文書調印のため代表団をマニラに派遣するよう命じます。
それが、のちに「ミドリ十字機」と呼ばれる命がけの飛行任務の始まりでした。
次回は、このわずか4日間に起きた知られざる危機と、ミドリ十字機が直面した数々の危険を、時系列で追っていきます。
8月15日 — 玉音放送は“戦争終結”ではなかった
1945年8月15日正午。
ラジオから流れた天皇の肉声に、日本中が耳を澄ませました。これが後に「玉音放送」と呼ばれる、ポツダム宣言受諾を告げる放送です。
多くの国民は「これで戦争は終わった」と胸をなで下ろしたでしょう。
しかし、その認識は大きな誤解でした。
戦争はまだ終わっていなかった
国際法上、戦争の終結は単なる宣言や放送では成立しません。
降伏文書の正式調印、占領軍の進駐、そして武装解除が完了するまでは、あくまで戦争状態が続きます。
つまり、8月15日の時点では「戦争終結の意思表示」はあっても、法的にも軍事的にも戦争は続行中でした。
「徹底抗戦」を叫ぶ部隊
国内には、玉音放送を受け入れず戦いの継続を望む部隊も少なくありませんでした。
その象徴が神奈川県の厚木航空隊です。
指令・小園安名は玉音放送の直後に「部隊独立宣言」を発し、独自の戦闘態勢に突入。
航空機を飛ばし、全国に決起を促すビラまで撒くという、事実上の反乱行動に出ました。
米軍の警戒 — 「ブラックリスト作戦」
連合国軍も、このような“暴発”を事前に想定していました。
特にアメリカは、降伏に従わない日本軍拠点を速やかに制圧する「ブラックリスト作戦」を準備。
必要とあれば武力で鎮圧し、日本本土への占領を確実に実行する構えを見せていたのです。
玉音放送の日は、日本人の記憶の中で「戦争が終わった日」として語られます。
しかし実際には、その裏で「徹底抗戦」を望む勢力と、戦争を終わらせたい勢力がせめぎ合う危うい時間が流れていました。
終戦は、放送と同時に訪れたのではなく、混乱と緊張の中で徐々に形を取っていったのです。
8月16日以降 — ソ連の北海道進攻の危機
1945年8月15日。玉音放送が流れ、日本全土に「戦争が終わった」という安堵の空気が広がろうとしていました。
しかし、その翌日から、北の海では新たな脅威が迫っていました。
それは、ソ連による北海道占領の危機です。
ソ連の対日参戦
ソ連は1945年8月8日、日ソ中立条約を一方的に破棄し、日本に宣戦布告しました。
そして終戦直前から千島列島や南樺太へ侵攻を開始。
本来なら停戦が成立するはずの8月15日を過ぎても、進軍の手を緩めることはありませんでした。
ソ連の立場は明確でした——「戦争はまだ終わっていない」。
北海道分割占領案
@lrazickytgg ”太平洋戦争ラストミッション”戦後日本の命運を分けた緑十字機#ABEMA #戦争 #ドキュメンタリー #終戦 ♬ original sound – ABEMA.jdp
さらに8月16日、ソ連はアメリカに対し、驚くべき提案を行います。
それは「釧路〜留萌を結ぶ線以北の北海道をソ連が占領する」という案でした。
もしこの案が通れば、日本はドイツと同じく、東西に分割統治されていた可能性があります。
そして北海道の北半分は“ソ連圏”として冷戦の最前線になっていたかもしれません。
急務となった降伏文書調印
アメリカはこのソ連案を拒否しましたが、状況は極めて危ういものでした。
ソ連軍の動きが加速すれば、占領の既成事実を作られる危険が高まります。
そのため、アメリカは一刻も早く日本に降伏文書を調印させ、連合国による占領統制を確定させる必要がありました。
この緊迫した外交と軍事のせめぎ合いが、のちに「ミドリ十字機」派遣の背景となるのです。
北海道は結局占領を免れましたが、それは偶然ではありませんでした。
8月16日からの数日間、日本は“北方の赤い影”と“南方から迫る連合国”の板挟みにあったのです。
3. 「ミドリ十字機」派遣任務
マッカーサーの命令
1945年8月17日、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーは、日本政府に対し命令を発しました。
——「日本代表をマニラに派遣し、降伏文書調印に関する打ち合わせを行え」。
この任務は単なる外交訪問ではありません。
相手は戦勝国、しかも国際的にはまだ戦争状態。交渉が決裂すれば、代表団は拘束されるか、その場で命を絶つ覚悟が必要でした。
選ばれた三人
危険を承知で選ばれたのは、陸軍から川辺虎四郎中将、海軍から横山一郎少将、外務省から奥村勝蔵。
いずれも軍と政府を代表する高官であり、戦争責任を背負う立場の人々でした。
彼らはマニラ行きが片道になる可能性を理解し、遺書をしたためて出発に臨みます。
「ミドリ十字機」
マッカーサーは「代表団は空路で来い」と指示。
その際、機体は白く塗装し、胴体と翼には大きく緑色の十字を描くことが条件でした。
これは国際的な「無害飛行機」の証であり、攻撃されないための目印です。
この特殊塗装の輸送機が、後に「ミドリ十字機」と呼ばれます。
@lrazickytgg ”太平洋戦争ラストミッション”戦後日本の命運を分けた緑十字機ドキュメンタリー#ABEMA #戦争 #ドキュメンタリー #終戦 ♬ original sound – ABEMA.jdp
ミドリ十字機、危機の空路 — 8月19日・木更津発
07:00 木更津飛行場出発
1945年8月19日、午前7時18分。
快晴の空の下、木更津飛行場(現在の陸上自衛隊木更津駐屯地)にミドリ十字機が静かに並ぶ。
極秘任務として、日本代表をマニラに派遣するこの飛行は、終戦直後の混乱と徹底抗戦派の妨害という危険を伴っていた。
厚木航空隊の妨害を避けるため、南回りの迂回ルートを選択。パイロットの須藤機長は、緊張と冷静さを同時に抱えながら操縦桿を握る。
@lrazickytgg ”太平洋戦争ラストミッション”戦後日本の命運を分けた緑十字機ドキュメンタリー#ABEMA #戦争 #ドキュメンタリー #終戦 ♬ original sound – ABEMA.jdp
08:20 厚木航空隊の追撃
南方ルートを進むミドリ十字機。突然、無線から緊急報告が入る。
「敵機発見!」
厚木飛行場からゼロ戦部隊が出撃しており、追撃は間一髪。
須藤は海面すれすれに高度を下げ、太陽を背にジグザグ運動で回避を試みる。
「ここで振り切る…!」
雲と日光を盾に、ゼロ戦の追撃を巧みにかわし、九州上空で出迎えの米軍機との合流に成功。
伊江島到着直前の緊迫
午後0時40分、沖縄北西の伊江島上空に到達。
しかし、ここで1番機に異変が発生。着陸用フラップが故障し、操作不能に。
米軍基地の管制官は緊張し、周囲には数千の米兵が集まる中、須藤は操縦桿を握りしめ、機体を短い滑走路に進入させる。
フラップは使えず、猛スピードのまま滑走路へ。米軍機との衝突寸前の状況も、須藤の冷静な判断と巧みな操縦で回避。
観衆は息を呑み、カメラマンは固唾を飲んでその瞬間を捉える。
@lrazickytgg ”太平洋戦争ラストミッション”戦後日本の命運を分けた緑十字機|ドキュメンタリー#ABEMA #戦争 #ドキュメンタリー #終戦 ♬ original sound – ABEMA.jdp
歴史的着陸
ついに、1番機と2番機は無事に伊江島の滑走路に着陸。
飛行隊員11人は島に残り、整備と後続任務の準備に当たる。
そして、代表団16人は米軍のC-54輸送機に乗り換え、マニラへ向かう。
このミドリ十字機の飛行は、全世界に生中継され、終戦への期待と日本の降伏への道筋を示す歴史的瞬間となった。
4. 伊江島からマニラへ — 降伏文書調印前夜
沖縄での一夜
1945年8月19日、正午過ぎに伊江島飛行場へ着陸した「ミドリ十字機」。
代表団を待っていたのは、物々しい米軍の警戒体制でした。
滑走路の周囲には武装兵士が並び、機体を降りると即座に身体検査と所持品の確認が行われます。
連合国側の視線は鋭く、「降伏国の使者」としての重みがその場の空気を張り詰めさせていました。
米軍機でフィリピンへ
伊江島で一泊した代表団は、翌20日朝、米軍のC-54輸送機に乗り込みます。
この機体は太平洋戦域の要人輸送にも使われる大型機で、内部には武装兵の姿もありました。
目的地は、マッカーサーの司令部が置かれたフィリピン・マニラ。
南下するにつれて、窓の外には青い海と雲の切れ間からの島影が見え、戦場から離れていく感覚が徐々に広がります。
マニラ到着
同日午後、マニラ郊外のニコルス飛行場に到着。
ここでも厳重な警戒のもと、代表団は米軍将校の出迎えを受けます。
ただし笑顔はなく、事務的かつ冷徹な応対。
代表団はそのまま米軍施設に護送され、翌日の会談に備えます。
降伏条件の最終調整
8月21日、マニラで行われた会談では、降伏文書の署名方法、調印式の場所、占領軍の進駐順序、武装解除の手順などが細かく詰められました。
アメリカ側は特に「無条件降伏の履行」を徹底する姿勢を崩さず、武装解除の即時実行を強く求めます。
日本側は時間的余裕を求めましたが、マッカーサーは譲らず、期限を明確に区切りました。
5. 帰還時のトラブル — 不時着と“8時間半遅れ”の奇跡
ミドリ十字機がマニラでの協議を終え、日本へ戻る工程は“順調”どころか、連続トラブルの連鎖でした。ここでは、伊江島出発から本土帰着までを、起きた問題ごとに細かくたどります。
① 伊江島での機体トラブル:2番機ブレーキ喪失
- 日時:8月20日夕~夜
- 概要:帰路に向けた出発準備中、2番機のブレーキ油圧がゼロになり、牽引車(トラクター)にぶつかって停止。
- 結果:修理の時間的余裕がなく、1番機のみで夜間飛行に切り替え。
- リスク:護衛なしの単機飛行、さらに「反乱勢力に航跡を掴まれにくい時間帯」を狙った夜間発進という高リスク運用に。
マッカーサー側は日本本土到着予定を把握しており、「20日 18:30 伊江島発 → 23:30 木更津着」の概算を日本側へ打電済み。単機運用でも遅延は許されない緊迫状況でした。
② 本州上空での燃料異常:想定外の“急減”
- 日時:8月20日深夜、紀伊半島上空
- 症状:計器上、燃料が急減していることを確認。
- 主張された原因(複数説)
- 単位取り違え説:米軍が「ガロン」、日本側が「リットル」で計測し、積載量の認識がズレた。
- 整備点検漏れ説:増設タンク(胴体側)の確認不足で空のまま出発した。
- 共通点:いずれの説でも、残燃料で木更津までの直行は困難。海上投棄や夜間洋上不時着は致命的となりうるため、陸岸沿いに緊急着陸地点を探索。
- 乗員の話では、整備員が意図的に任務妨害を画策して燃料を補給しなかった。唯一、整備員の氏名は公表されていない。
③ 不時着の決断:鮫島海岸(天竜川河口東)
- 日時:8月20日 23時55分
- 場所:静岡県遠州灘沿いの鮫島海岸(天竜川河口の東側、砂浜が長く続く直線海岸)
- 着陸要素:
- 満月に近い月明かりで海面と砂浜の境界が視認可能。
- 高度を500mまで落とし、一発勝負の進入。
- 操縦:機長・須藤幸雄が副操縦士に衝撃姿勢を指示し、自ら単独操縦でタッチダウン。
- 機体状態:前部が砂浜、後部が浅い海中に入り停止。乗員全員無事、降伏関連文書も無事という“最良の不時着”。
④ 深夜の救助:漁師と警防団、そして村人たち
- 発見:日付が変わった8月21日未明、漁師2名が機体を発見。
- 連携:鮫島集落の警防団が駆けつけ、雑貨店「太田屋」で隊員が休息・連絡準備。
- 通信:近隣の(当時の)袖裏飛行場へ電話連絡。ここは小型機訓練用で実用機がなく、浜松飛行場へ陸送する案に切替。
- 周辺の混乱:夜明けとともに見物人が集まり、座席クッションや標識棒など機体の一部が持ち去られる騒ぎも発生(のちに“記念物”として保管された例も)。
⑤ 陸送と再飛行:浜松→調布へ
- 移動:軍用トラックで天竜川を渡り浜松飛行場へ。市街は空襲と艦砲射撃で焼け野原。
- 機体確保:たまたま重爆「飛龍(ひりゅう)」が浜松に残留。徹夜で整備・修理。
- 再離陸:8月21日 6時30分、浜松発。
- 到着:同 8時頃、調布飛行場に着陸。
- トータル遅延:木更津直帰の計画と比べ、約8時間半の遅れにとどめる“奇跡的なリカバリー”。
⑥ 影響と意味:無欠進駐への道筋
結果として、8月28日 先遣隊上陸/8月30日 マッカーサー厚木到着が“無欠”で実現し、北海道分割や戦闘再開の最悪シナリオを回避。
調布到着直後、大本営はただちに全国へ進駐日程と武装解除要領を通達。
最大の火種だった厚木航空隊には、「8月24日18時までに移動」「弾薬・魚雷は海中投棄」などの強制措置が発出。
この“帰還時のトラブル”は、単なる事故の羅列ではありません。
「文書と人員を必ず生かして届ける」という任務最優先の判断と、現場の即応力、地域住民の協力が複層的に噛み合った結果、終戦を実現する最後のピースが間に合ったのです。
8月19日〜20日 — 厚木反乱鎮圧と無欠進駐の舞台裏
終戦直後の日本。玉音放送で戦争終結は告げられたものの、現場ではまだ混乱が続いていた。特に神奈川・厚木の航空隊は、「徹底抗戦」を掲げる反乱の中心だった。
ここを制圧しなければ、マッカーサー率いる連合国軍の無欠進駐(日本全土への安全な占領)は不可能であった。
厚木航空隊の動向
玉音放送直後、厚木航空隊は独自の行動を開始。「部隊独立宣言」を掲げ、戦闘態勢を強化。
空にはゼロ戦が配備され、南回りで飛行中のミドリ十字機を追撃。
これに対し、米軍と連携した日本政府は迅速な鎮圧作戦を決断する。
反乱鎮圧作戦
厚木航空隊の追撃を受けたミドリ十字機の離陸・航行は、単なる代表団派遣の任務ではなく、反乱部隊の動向を探り、無欠進駐への布石でもあった。
- 米軍は戦闘機と輸送機を即座に展開
- 日本政府は陸海空の信頼できる部隊を動員
- 厚木基地に向け、心理的圧力と戦力展示を同時に実施
この連携作戦により、厚木航空隊は戦闘続行の意思を抑えられ、無血での降伏が実現した。
無欠進駐の確保
反乱鎮圧後、マッカーサーの指揮下で連合国軍の安全な日本全土進駐が可能となる。
- 各地の反乱勢力は自発的に武装解除
- 主要都市への占領部隊の展開が迅速化
- 民間人や代表団への被害を最小化
厚木航空隊の迅速な鎮圧は、単なる軍事作戦の成功ではなく、戦後日本の安全かつ秩序ある占領の実現に直結した歴史的瞬間であった。
終戦直後の教訓
この事例は、戦争終結の「形式」と「現場の現実」が必ずしも一致しないことを示している。
- 玉音放送だけでは戦争は終わらず
- 現場の部隊の意志次第で事態は変わる
- 正確な情報と迅速な対応こそ、平和的な占領を実現する鍵であった
厚木航空隊の無血鎮圧は、日本における平和の種を守った歴史的決断として、今日まで語り継がれている。
まとめ
戦争終結の玉音放送が行われた直後の日本は、一見平穏に見えましたが、実際には依然として一触即発の危機が続いていました。
各地の部隊の中には徹底抗戦を主張する者も存在し、特に厚木航空隊では反乱の兆しがあったため、戦後の占領や武装解除の円滑な実施に大きな障害となる可能性がありました。
そうした中で実施された厚木航空隊の無血鎮圧は、戦闘を回避しつつ、秩序を守るという極めて難しい判断のもとに行われたものでした。
この歴史的な決断によって、日本国内での占領が安全かつ円滑に進められる基盤が築かれ、混乱の中で平和を守るための指導者たちの判断の重要性を後世に伝える教訓となっています。
緑十字機の命がけの任務や現場の努力も含め、これら一連の行動は、戦争の終結という大きな節目において、単なる勝利や敗北ではなく、人命と秩序を最優先に考える決断がいかに重要であったかを示す象徴的な出来事として、今日に至るまで語り継がれています。
| 日付 | 主な出来事 |
|---|---|
| 8月15日 | 玉音放送:昭和天皇がポツダム宣言受諾を国民に伝達。戦争状態は継続。厚木航空隊の一部が徹底抗戦を呼びかけ。 |
| 8月16日 | ソ連が北海道占領を米国に打診。正式降伏文書調印の必要性が急務に。 |
| 8月17日 | マッカーサーが日本代表をマニラに派遣せよと指令。陸軍・海軍・外務省から代表者3名を選定。任務は極めて危険。 |
| 8月19日 | 緑十字機(ミドリ十字機)が木更津飛行場から離陸。厚木航空隊の追撃を回避するため南回りルートを選択。九州上空で米軍機と合流。伊江島に着陸、1番機はフラップ故障のトラブルをパイロット須藤が回避。 |
| 8月20日 | 日本代表がマニラ到着、連合国と終戦交渉開始。厚木航空隊の無血鎮圧に成功し占領準備が円滑に進む。 |
| 8月21日~25日 | 降伏文書調印に向けた交渉進展。日本国内での秩序維持や主要施設管理計画を進行。 |
| 8月26日~28日 | 降伏文書調印の最終準備。米軍進駐のルート確保や軍事施設占領計画。 |
| 8月29日 | 日本政府が降伏文書内容を最終承認。占領部隊の主要都市進駐が開始。 |
| 8月30日 | マッカーサーが厚木基地に上陸。無血進駐が実現し、国内での戦闘行為はほぼ停止。事実上の戦争終結が確立。 |