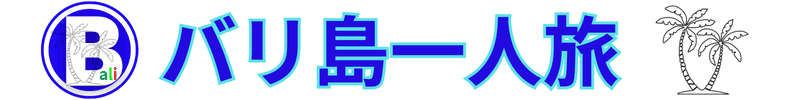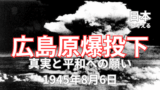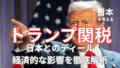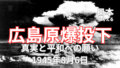1945年8月9日午前11時2分──長崎の空に、世界で二度目の原子爆弾が炸裂しました。
一瞬にして街は炎と瓦礫に包まれ、数万人の命が奪われ、助かった人々も放射線による長い苦しみにさらされました。
戦争の終結を早めたとされるこの出来事は、同時に人類史上最も深い傷を残した悲劇でもあります。
本記事では、長崎原爆投下の背景、被害の実態、そして今も続く影響と平和への取り組みについて、歴史的事実と証言をもとにたどります。
あの日何が起き、何が失われ、そして私たちはそこから何を学ぶべきなのか──記憶と教訓を次の世代へ伝えるために。

本文を読まなくてもいいから、鈴木長崎市長の「平和宣言」の動画を見てほしい。👇
@dorosien28 8月9日の長崎平和祈念式典── 長崎市の鈴木市長が最後まで意志を貫いたことに最大限の賛辞を送ります。… 全文 https://mainichi.jp/articles/20240807/k00/00m/040/157000c
♬ original sound – dorosien28
1. 歴史的背景
@heiwafilm 余りにも衝撃な体験とその光景は、何十年もの月日が経とうとも消え去る事はありません。 あの時の原爆の音も、原爆の匂いも、その全てを今も心に焼き付けておられます。 #記憶 #歴史 #ドキュメンタリー #平和な日常 #戦争体験 #長崎 #平和 ♬ ずっと心の中に生き続けるピアノメロディー – naopapa
戦況の悪化と終戦への道
1945年夏、日本はすでに敗戦が目前となっていました。太平洋戦争は米軍による本土空襲が激化し、東京や大阪をはじめとする大都市は焼け野原と化していました。さらに7月26日には、アメリカ・イギリス・中国(後にソ連も参加)が発表したポツダム宣言により、日本に無条件降伏が要求されます。しかし日本政府はこの宣言を公式に受諾せず、「黙殺」という姿勢を示しました。米国はこれを拒否と受け取り、原子爆弾の使用を決断します。
広島への原爆投下
8月6日午前8時15分、米軍のB-29爆撃機「エノラ・ゲイ」が広島市上空でウラン型原子爆弾「リトルボーイ」を投下。爆発により市中心部は壊滅し、約14万人が1945年末までに死亡しました。
この衝撃的な被害にもかかわらず、日本政府は即時降伏を決定しませんでした。
長崎が標的となった理由
当初、米軍は次の投下目標として小倉市(現・北九州市小倉北区)を予定していました。小倉は重要な兵器工場や軍事施設が集中しており、戦略的価値が高かったためです。
しかし、8月9日の投下当日、小倉市上空は厚い雲や煙幕で視界が悪く、目標地点の確認ができませんでした。煙幕の一因には、前日に行われた米軍の空襲による黒煙や、日本軍の意図的な防御もあったとされています。
投下目標の変更
爆弾を抱えたB-29「ボックスカー」は、燃料の残り時間も限られる中で決断を迫られます。乗組員は次の予備目標である長崎市へ進路を変更しました。長崎は当時、日本有数の造船都市であり、三菱造船所や兵器工場などの軍需施設が集中していたため、米軍にとって戦略的な価値がありました。
投下直前の状況
長崎上空も雲が多く、最初は視認が困難でしたが、投下直前に雲の切れ間から目標を確認できたため、午前11時2分、「ファットマン」が浦上地区上空約500メートルで炸裂しました。
この一連の経緯は、長崎への原爆投下が偶然の連鎖の中で起きたという歴史的事実を物語っています。
2. 投下の概要
投下日と時刻
- 日付:1945年8月9日(木曜日)
- 時刻:午前11時2分頃(日本時間)
この日は早朝からB-29爆撃機「ボックスカー」がテニアン島の北飛行場を離陸し、長崎への航路に入りました。当初の目標である小倉市を飛び立ち、長崎市上空に到達したのは午前10時50分前後。燃料の残量が限られる中、目標確認後わずか十数分で投下が行われました。
爆弾の名称と構造
- 名称:「ファットマン(Fat Man)」
名前の由来は、丸みを帯びた砲弾型の外形がふくよかな人のシルエットに似ていたことから。 - 型式:プルトニウム型原子爆弾(インプロージョン方式)
内部にプルトニウム-239を球状に配置し、周囲に高性能爆薬を取り付けて同時爆発させ、核分裂を起こす仕組み。広島型(リトルボーイ)のウラン方式に比べ、より複雑で精密な設計を必要としました。 - 重量:およそ4.5トン
- 全長:3.25メートル
- 直径:1.52メートル
投下の高度と爆発の位置
- 投下高度:約9,000メートル(飛行高度)
- 爆発高度:地上約500メートル
爆発高度は最大の破壊効果を生むよう計算されました。空中で爆発することで、爆風と熱線が地表全体に広がり、山や建物の影による遮断を最小限に抑える狙いがありました。
爆発規模とエネルギー
- 威力:推定21キロトン(TNT火薬換算)
これは、第二次世界大戦中に使用された最大規模の通常爆弾の数千倍に相当します。
爆発の瞬間、数百万度の高温が発生し、直径数百メートルの火球が形成されました。 - 熱線:爆心地付近では表面温度が3,000〜4,000℃に達し、鉄も瞬時に溶ける熱量。
- 爆風:時速1,000kmを超える衝撃波が広がり、半径2km以内の建造物はほぼ全壊。
- 放射線:初期放射線と残留放射線により、多くの被爆者が急性症状や長期的な健康被害に苦しむことになりました。
投下後の状況
爆発から数秒で市街地は炎に包まれ、浦上地区を中心に壊滅状態となりました。山に囲まれた長崎特有の地形により、被害は広島と異なる分布を示しましたが、それでも数万人の命が瞬時に失われました。
米軍の機体は爆発後の衝撃波を回避するため急旋回し、沖縄経由で基地へ帰還しました。
| 項目 | 広島原爆 | 長崎原爆 |
|---|---|---|
| 投下日 | 1945年8月6日 午前8時15分 | 1945年8月9日 午前11時2分 |
| 爆弾名 | リトルボーイ(Little Boy) | ファットマン(Fat Man) |
| 型式 | ウラン型(ガンバレル方式) | プルトニウム型(インプロージョン方式) |
| 重量 | 約4トン | 約4.5トン |
| 全長 / 直径 | 3.0m / 0.71m | 3.25m / 1.52m |
| 威力 | 約15キロトン(TNT換算) | 約21キロトン(TNT換算) |
| 爆発高度 | 約600m | 約500m |
| 爆心地 | 広島市中区相生橋付近 | 長崎市浦上地区 |
| 当時の人口 | 約35万人 | 約24万人 |
| 死者(1945年末まで) | 約14万人 | 約7万4千人 |
| 負傷者 | 約7万人 | 約7万5千人 |
| 被害の広がり | 平地で広範囲に拡散し、約13km²がほぼ壊滅 | 山に囲まれた地形で被害範囲が限定的だが、爆心地付近は壊滅 |
| 特徴的被害 | 官公庁街・商業地が直撃し都市機能が崩壊 | 浦上天主堂や軍需工場が破壊、宗教施設や民家の損失が大きい |
3. 被害の実態
@zosama24 ♬ 切ない、悲しい、美しいピアノソロ – 棚橋 歩
爆発地点と初期被害
1945年8月9日午前11時2分、原子爆弾「ファットマン」は長崎市浦上地区上空約500メートルで爆発しました。爆心地周辺は一瞬で数千度の高温に包まれ、半径約1km以内のほぼ全ての建物が跡形もなく吹き飛びました。浦上天主堂や三菱兵器製作所などの大規模施設も壊滅し、市街地の一部は火災によって焼き尽くされました。
人的被害
- 死者:推定7万4千人(1945年末まで)
その多くは爆発直後の熱線や爆風で命を落とし、残りは火傷や放射線障害、火災によって亡くなりました。 - 負傷者:推定7万5千人以上
全身火傷や外傷、放射線による急性症状(吐き気・脱毛・出血など)が多く見られました。 - 爆心地近くでは、人影が地面や壁に焼き付く「原爆影」が残るほどの高熱でした。
建物被害
- 全焼・全壊:市街地の約36%(約1万9千戸)
- 半壊・一部損壊:数千戸に及ぶ
- 浦上地区を中心とした平地部は壊滅しましたが、長崎市は山に囲まれた盆地状の地形のため、爆風は谷筋を抜ける形で広がり、広島のように全方向に一様な破壊は及びませんでした。
地形が与えた影響
長崎は三方を山に囲まれており、爆風や熱線は地形によって部分的に遮られました。そのため、広島に比べると被害範囲は相対的に狭かったものの、爆心地付近の破壊力は極めて高く、浦上地区は完全に壊滅しました。谷間に沿って被害が集中し、一部の斜面にあった家屋は爆風で吹き飛ばされるか、山火事によって焼失しました。
二次被害とその後
爆発後、市内各所で火災が発生し、負傷者の救助や消火活動はほとんど行えない状況でした。さらに、放射線による後遺症が生き残った被爆者を長く苦しめました。数日後には高熱や吐き気、白血球減少といった急性放射線症状が現れ、数週間から数か月の間に亡くなる人も多くいました。
4. 放射線被害
急性放射線障害
原爆爆発時には、初期放射線(主に中性子線とガンマ線)が瞬間的に放出されました。爆心地からおよそ2km以内にいた人々は大量の放射線を浴び、爆発直後から、または数時間後に以下の症状が現れました。
- 吐き気・嘔吐:被曝から数時間で発症
- 脱毛:数日〜数週間で急激に髪が抜け落ちる
- 下痢・発熱・全身倦怠感
- 皮下出血や歯茎からの出血(血小板減少による)
これらは骨髄や免疫系が深刻に損傷したことによるもので、多くは数週間〜数か月で命を落としました。
晩発性障害
被爆後数年から十数年を経て、白血病やがん(甲状腺がん・乳がん・肺がんなど)が増加しました。特に白血病は被爆5〜10年後にピークを迎えたと報告されています。また、皮膚障害や白内障、慢性肝炎なども多く見られました。
医療体制の崩壊
爆発直後、長崎市内の医療施設は壊滅的な被害を受け、医師や看護師も多数死亡しました。応急手当すら行えない状況で、多くの負傷者は放置されたまま命を落としました。米軍が本格的に被爆調査を行ったのは終戦後で、日本人医師が詳細な放射線医学の研究を行える環境は当初ほとんどありませんでした。
社会的影響と差別
被爆者は戦後も、放射線の影響を恐れられ、結婚や就職で差別を受けることがありました。「被爆者は子どもが産めない」「病弱で働けない」といった誤った認識が広まり、多くの人々が精神的にも苦しむことになりました。
5. 長崎を襲った二重の悲劇(詳細版)
浦上天主堂の倒壊
長崎市浦上地区は、日本最大のカトリック集落として知られていました。中心にあった浦上天主堂は、レンガ造りとしては東洋一の規模を誇る壮麗な建築物でしたが、爆心地からわずか約500メートルの距離にあったため、爆風と熱線で一瞬にして崩壊しました。長年の信仰の象徴は瓦礫と化し、多くの信徒が礼拝中や日常生活の中で命を奪われました。
若者たちの犠牲
戦争末期の長崎には、軍需工場で働くために全国から動員された学徒動員の学生や労働者が多く集まっていました。彼らは十代半ば〜二十代前半の若者で、爆心地近くの工場や作業場で作業中に被爆し、多くが即死または重傷を負いました。中には家族のもとに帰ることなく、疎開先や下宿先でひっそりと亡くなった学生もいました。
二重の喪失
長崎の原爆被害は、都市機能や住居の喪失だけでなく、宗教的象徴の破壊と未来を担う若者の命の喪失という二重の悲劇をもたらしました。これは単なる戦争被害を超え、地域文化や精神的支柱をも根こそぎ奪った出来事でした。
6. 戦後の影響と平和への誓い
復興と記憶の継承
戦後の長崎は、焦土と化した市街地の復興と同時に、原爆被害の記憶を後世に伝える取り組みを進めてきました。単に街を再建するだけでなく、核兵器の脅威を世界に訴える都市としての役割を担うようになりました。
原爆資料館(1966年開館)
1966年、爆心地近くに長崎原爆資料館が開館しました。館内には被爆した瓦礫や生活用品、焼け焦げた衣服、当時の写真や映像が展示され、原爆の恐ろしさと被害の実態を生々しく伝えています。また、核兵器廃絶の必要性を世界に発信する国際会議や教育プログラムも行われています。
平和公園(1955年完成)
1955年、爆心地の北側に平和公園が完成しました。園内中央には、彫刻家・北村西望による平和祈念像が立ち、右手は原爆の脅威を、左手は平和を象徴的に示しています。訪れる人々は、祈念像の前で犠牲者を悼み、世界の平和を願います。
平和宣言
毎年8月9日、長崎市では原爆犠牲者慰霊平和祈念式典が行われ、市長が「平和宣言」を読み上げます。宣言では、被爆者の苦しみと核兵器廃絶への願いを代弁し、世界の指導者に核廃絶を呼びかけます。この宣言は国連などを通じて世界各国に伝えられています。
7. 現代への教訓(詳細版)
長崎原爆投下は、核兵器がもたらす破壊力と深刻な人道的影響を人類に示した出来事でした。しかし、21世紀の今も、地球上には1万発を超える核兵器が存在し、その脅威は依然として続いています。核抑止論や軍事的均衡という名目で存続してきた核兵器ですが、一度使用されれば、被爆地で見られたような惨状が再び繰り返されることは明白です。
証言を受け継ぐ
被爆から80年近くが経過し、直接の体験者は年々少なくなっています。その証言や記録を正確に受け継ぎ、戦争と核兵器の恐ろしさを次の世代に伝えることは、被爆地に限らず世界中の人々の使命です。近年では映像記録やVR技術を用いた証言保存、国際的な平和教育プログラムが広がりを見せています。
核兵器のない世界へ
長崎は広島とともに、「二度と同じ悲劇を繰り返さない」というメッセージを発信し続けています。それは単なる過去の記録ではなく、未来を守るための行動指針でもあります。
核兵器の廃絶は困難な課題ですが、長崎の経験が示すのは一つの真実――人類と核兵器は共存できないということです。

太平洋戦争は日本が始めたものの、その終結の名のもとに、米国は広島と長崎に原子爆弾を投下しました。
しかし、戦争に「正義」はありません。
この歴史の中で、広島・長崎で犠牲となった数多くの命は、決して無駄にされてはならないと強く感じます。
彼らの魂が安らかでありますように、そして二度と同じ悲劇が繰り返されないように。
私たち一人ひとりが心に刻み、行動することが求められています。
世界から核兵器が一日も早くなくなり、平和な未来が訪れることを、心から願ってやみません。