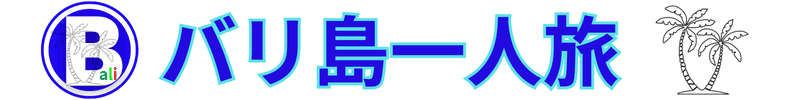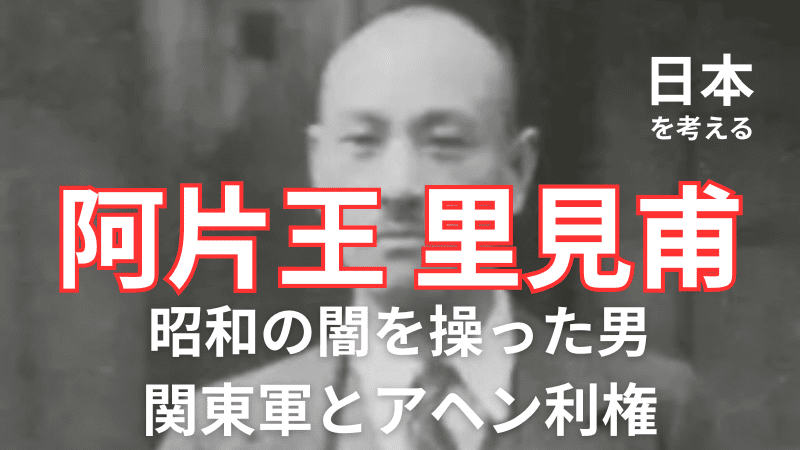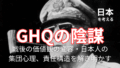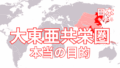「日本はなぜ、あんなにも戦争に突き進んだのか?」
「本当に軍や政府だけが主導していたのか?」
「戦争にお金はどうやって流れていたのか?」
こうした疑問を持ったことはありませんか?
歴史の教科書やニュースでは語られない、「裏の顔」をもつ人物たちが、確かに存在していました。
そのひとりが 里見甫(さとみ・はじめ) です。
一般にはほとんど知られていない名前ですが、彼は昭和初期から日中戦争、そして太平洋戦争へと続く歴史の裏側で、
莫大な“戦争資金”を動かした人物です。
しかもその手段は、驚くべきことに──アヘンの密売でした。
この記事では、軍人でも政治家でもない一介の実務家が、
いかにして国家の大義と裏金の流れを操ったのか。
そして彼が信じた「理想」とは何だったのか。
歴史の裏側に踏み込みながら、一緒に探っていきましょう。
1. 少年時代と孫文との出会い
小倉で生まれた柔道少年
明治29年(1896年)、里見甫は九州・小倉の町に生まれました。
父は地域を回る開業医でしたが、決して裕福とは言えない家庭環境。里見少年は勉強に没頭するよりも、柔道や遊びに熱中するやんちゃな少年でした。
学校の成績は悪く、担任教師からも厳しい目で見られていた彼。しかし、身体能力と胆力には並外れたものがあり、柔道では地元で知られた存在になっていきます。
中学生で中国革命の父・孫文と接触
そんな里見少年の人生を大きく変える「出会い」が、彼がまだ中学生だったころに訪れます。
時は辛亥革命の直後。日本国内に亡命していた孫文(そんぶん)──中国近代革命の父──が小倉を訪問します。
当時、孫文は日本の政財界人や留学生とのネットワークを広げており、講演や訪問先には多くの見物人が集まりました。
ある日、孫文が小倉中学を訪れた際、柔道の試合が披露されることになりました。そこに登場したのが、少年・里見甫です。
運命を変えた「5人抜き」と留学への誘い
里見はこの日、次々と相手を投げ飛ばし、5人連続で勝ち抜く「五人抜き」を達成します。見物していた孫文は、目を細めてこう言ったといいます。
「立派な腕前だ。将来、中国に来て柔道を教えてくれないか?」
当時まだ10代の里見少年にとって、この一言は衝撃的でした。
日本では見下されがちだった自分が、外国の偉人から必要とされた。
その感動と誇らしさは、やがて彼を「中国へ渡る」という人生の決断へと導きます。
この出会いがなければ、彼は普通の柔道好きの青年で終わっていたかもしれません。
しかし孫文の一言が、後に彼を満州の黒幕、そしてアヘンを動かす影の実務家へと変えていく、最初の「導火線」となったのです。
2. 中国留学と人生の転機
難関の東亜同文書院大学へ──学力ではなく、意志で突破した留学
孫文との出会いがきっかけとなり、里見甫はある決意をします。
「中国に行きたい。現地で学び、将来、役に立てる人間になりたい」
しかし、彼が目指した東亜同文書院大学(上海)は、当時の日本人学生にとって超難関のエリート校。
現地中国を理解し、語学と国際感覚を備えた人物を育てるという理念のもと、成績や品行に厳しい基準が設けられていました。
柔道少年だった里見には、学力という点では不利な状況。しかし、彼の熱意を感じ取った父親が動きます。
福岡市に掛け合い、「派遣留学生」としての推薦を得て、奇跡的に合格。こうして、彼は上海の地に足を踏み入れたのです。
中国語と実践的ビジネス感覚を武器に
東亜同文書院では、中国語を徹底的に学ぶと同時に、商業・経済・外交の実務を叩き込まれます。
教室だけでなく、現地の市場や役所に通い詰める“現場主義”の教育は、まさに里見向き。
彼はみるみるうちに語学力と実地感覚を身につけていきました。
卒業後、彼は日本の貿易会社に就職し、ビジネスマンとしての第一歩を踏み出します。
上海を中心に、商品輸出入や中国側の商人との交渉に関わり、若くして実務の最前線に立ちました。
戦争と失業、そして再び中国へ
しかし、時代は動きます。
第一次世界大戦後の経済不況は、アジアにも大きな打撃を与え、里見の勤務先も倒産。
彼は帰国を余儀なくされます。
ただ、ここで彼は終わりませんでした。
再び上海へ渡り、今度は新聞記者として再出発します。現地取材と情報収集を通じて、政治・軍事・経済の動きに精通し、中国人の人脈も拡大していきました。
記者としての活動を通じて、彼は「情報の価値」と「現地との信頼構築の力」を身をもって学んでいきます。
この時期こそ、のちに彼が関東軍の裏情報担当やアヘン取引の実務家として重宝される土台を築いた、人生の本当の転機だったのです。
3. 関東軍との接近と政治工作
国民党幹部と接触、満州の工作活動へ
新聞記者として上海に根を張った里見甫は、表向きは民間人でありながら、裏では日本の情報機関や軍関係者と密接な関係を築いていきます。
とりわけ注目すべきなのは、当時の中国国民党の幹部と接触し、その内情を日本側に報告していたことです。
彼は語学だけでなく、人間関係を構築する力に秀でており、中国人たちの懐に自然と入り込んでいきました。
「日本のスパイ」ではなく「信頼できる対話者」として現地での立場を築いたことが、彼の最大の強みでした。
この柔軟なスタンスとネットワークを重視したのが、のちに彼を「裏の実務者」として起用する関東軍でした。
張作霖爆殺事件と軍とのパイプ
1928年、満州の地で歴史を揺るがす事件が起こります。
それが、関東軍による張作霖爆殺事件。日本の軍部が、自国と協調的だったはずの中国軍閥リーダーを列車ごと爆破し暗殺するという、衝撃の暴挙です。
当時、これを「中国人による犯行」と偽装しようとした日本側には、中国内部の情勢に精通した“協力者”が必要不可欠でした。
里見甫が直接この作戦に加担した証拠はありませんが、彼が満州や北支の工作活動に関わり始めたのはこの頃と一致しており、
関東軍の政治工作部門とのパイプを深めていたことは確実です。
里見は次第に、「民間人として動けるスパイ、外交官、ビジネスマン」という三位一体の役割を担いはじめるのです。
「満州国通信社」の設立とプロパガンダ戦略
1932年、関東軍が主導して建国された傀儡国家──満州国。
表向きは独立国家を装っていましたが、実態は日本帝国の戦略拠点であり、その正当性を世界にアピールするための広報戦略(プロパガンダ)は欠かせない任務でした。
ここでも、白羽の矢が立ったのが里見甫です。
彼は電通や新聞連合(現在の共同通信の前身)とも連携しながら、「満州国通信社」を設立。
情報の発信、国内外メディアの誘導、満州国の正当化など、広報・宣伝を一手に担う中枢を築き上げます。
重要なのは、これが単なる報道機関ではなく、情報戦のための兵器として運用されていたことです。
里見は「報道の自由」ではなく、「国家の情報戦略」を信じていた。
民間人という立場で、彼は軍や政府が手を出しにくい領域を代行し、
言葉と情報、そして人脈を使って戦争への地ならしを着実に進めていったのです。
4. 闇の金脈──アヘン利権の実務責任者
関東軍の資金源となったアヘン取引
表向きは「理想国家」だった満州国。
しかしその美辞麗句の裏側には、国家を動かすための汚れた資金源がありました。
それが──アヘンです。
国際的には禁止薬物であるアヘンですが、満州では公然と流通・販売され、国家の財源となっていました。
特に中国人の中毒者は多く、そこに依存して金を回す仕組みは、最初から計画的に構築されたものでした。
そしてこのアヘン利権の実務を担った人物こそが、里見甫です。
関東軍は表立って手を出せない非合法活動を、彼のような“民間の顔を持つ協力者”に委ねることで、
アヘンを用いた資金調達スキームを隠密に、かつ効率的に進めていたのです。
機密費と非合法資金ルートの確立
里見の役割は、単なるアヘンの売買ではありませんでした。
彼が担っていたのは、売上金を「表の金」に洗浄し、日本軍の秘密活動に使えるようにするルートの構築と管理です。
具体的には──
- 中国国内のヤミ市場でアヘンを流通
- 得た利益を香港や上海経由で「合法資金化」
- 満州国や日本政府の軍事機密費、政治工作費として使用
これらのルートは、「日本政府の帳簿に載らない金」として、スパイ活動、反政府勢力の買収、国際世論工作に用いられました。
特に興味深いのは、里見がこうした資金の流れを**「国家のための実務」として割り切っていた形跡**があることです。
彼は決して暴力団のような反社会的存在ではなく、むしろ「理想を信じた民間の愛国者」という側面も併せ持っていました。
「理想の満州国家」の裏に広がる麻薬経済
「五族協和」「王道楽土」──
それが日本が掲げた満州国の理想像でした。
しかし、実態は麻薬による国家運営。アヘンは国家財政の3割を占める年もあったとされ、
まさに「アヘンなくして満州なし」と言っても過言ではない状況だったのです。
そして、里見甫はその中核にいた。
彼が作り上げたアヘンの物流・資金ルート網は、まるで民間の顔をしたインテリジェンス機関でした。
裏金、密輸、買収、そして報道統制──それらを民間人の立場で担った彼の存在は、軍や政府すら動かせる「もう一つの権力」だったのです。
「これは悪なのか?それとも必要悪か?」
読者であるあなた自身に、その判断を委ねたい。
5. 表の顔と裏の顔──矛盾と信念のはざまで
「文化人」里見甫──日中友好と理想国家建設を語る顔
上海や満州を舞台に活動していた里見甫は、当時のメディアでは「文化人」あるいは「日中交流の実務家」として知られていました。
彼の表の肩書は多岐にわたります──
- 満州国通信社の幹部
- 東亜経済調査会の要職
- 日中交流団体の文化代表
- 雑誌・新聞での寄稿者や評論家
その口から語られるのは、「五族協和」や「王道楽土」といった、理想主義にあふれたスローガン。
中国と日本が手を取り合い、新しい文明社会を築く──そう語る里見の姿に、人々は知的で穏やかな実務家という印象を抱いていました。
外交官でもなく、軍人でもなく、あくまで“民間”という立場から日中の未来を語るその姿は、信頼感を生み、
政府や関東軍すらも彼の「表の顔」を有効活用していたのです。
関東軍・政府高官と裏でつながる“影の実務者”
しかし、その裏側で動いていたのは、国家の表舞台では到底語れない闇の仕事でした。
里見は、
- 関東軍の政治工作部
- 満州国の特務機関
- 日本本国の外務・内務・陸軍省高官
…といった勢力と常時連絡を取り合いながら、
「表では動けない仕事」を静かに、しかし着実に進めていたのです。
アヘンの資金ルート構築もその一つですが、それだけではありません。
スパイの養成、対中宣伝のシナリオ作成、工作資金の隠蔽、反満分子の情報収集──
「戦争を進めるために必要だが、政府や軍が表では手を出せない任務」を、里見は“民間の顔”で代行していたのです。
ある意味で、彼は一介のスパイよりも危険で、
国家という巨大な存在の“最も敏感な神経系”の一部を担っていたと言えるでしょう。
信念──「軍のためではない、理想の満州のために」
だが、ここで重要な問いが浮かびます。
彼は、自分が「悪」をしているという自覚があったのか?
記録に残る彼の言葉や態度から見えるのは、単なる利得主義者ではない、一つの信念に縛られた男の姿です。
彼は、軍の暴走にも距離を取りながら、こう言い聞かせていたようです。
「私は軍のために動いているのではない。
満州国という、理想の国家を築くために必要な仕事をしているのだ」
もちろん、それは自己正当化にすぎなかったのかもしれません。
アヘンに苦しむ民衆の姿を見ながら、それでも“国家のため”と行動し続けた彼は、
正義と現実のあいだで苦悩し、分裂しながらも進み続けた存在でした。
だからこそ、彼の人生は「善か悪か」では割り切れないのです。
その人物は、英雄か。悪党か。あるいは──両方だったのか。
それを決めるのは、歴史ではなく、私たち一人ひとりの視点なのかもしれません。
6. 終戦と消えた巨影──戦後の沈黙と再評価
終戦とともに消えた「影の実務者」
1945年、日本は敗戦を迎えました。
満州国は崩壊し、関東軍は解体され、帝国主義の野望は音を立てて瓦解していきます。
そして──
その混乱の中で、里見甫という男もまた、公の歴史の表舞台から姿を消しました。
かつてアヘンを武器に資金を動かし、情報を操り、理想国家の建設を夢見た男は、
敗戦後、GHQや戦犯追及の動きにもかかわらず、なぜか裁かれることはありませんでした。
その理由には諸説あります。
- 戦争犯罪の立件が困難だったこと
- 戦後の米国諜報機関との接点
- あくまで「民間人」として活動していた立場のグレーさ
…いずれにせよ、彼は公的には「無罪」のまま、戦後を生き延びます。
沈黙と引退──語られなかった過去
戦後、里見は静かに表舞台から引退。
再び上海には渡らず、国内でごく限られた範囲の仕事に携わりながら、自らの過去を多く語ることはありませんでした。
当時の資料を読んでも、戦後の彼が取材に応じた記録はほとんどなく、
彼が何を思い、何を感じながら晩年を過ごしたのかは、今も謎に包まれています。
かつて軍の影として動き、時には国家の背骨を作るような実務にまで関与していた男が、
一転して「誰にも語られない存在」となったことに、時代の皮肉を感じずにはいられません。
再評価されはじめた“戦争の実務家”
21世紀に入り、情報公開や戦前史の再検証が進む中で、里見甫の名は「影の立役者」として再び脚光を浴びはじめました。
ジャーナリストや歴史家の調査により、
- アヘン利権と国家財政の関係
- 満州国通信社のプロパガンダ戦略
- 政治工作における“民間の役割”
などが明るみに出るにつれ、「あの時代を支えた人物の一人」として、冷静な評価が進んでいます。
彼は軍人でも政治家でもない。
それでも、歴史を裏側から動かした男だった──
そう認識されるようになった今、その存在はようやく、光と影の両方をまとった「実在の人物」として見つめられ始めているのです。
歴史の表には出なかったが、確かに歴史の芯にいた。
その名前が何を語るのかは、いまを生きる私たちに委ねられている。
7. なぜ今、里見甫を知るべきなのか(まとめ)
歴史は、表に出た者だけで作られているわけではない
日本と中国のはざまで、満州という「理想国家」の建設に奔走した民間人──里見甫。
彼の名を教科書で目にすることは、まずありません。
しかし、その背後で動かしていた資金、情報、戦略──
それは帝国日本のアジア政策を実行するうえで欠かせないピースでした。
軍や政府の陰に隠れた“影の実務者”こそが、時に歴史の本質を握っている。
その事実を、私たちはもっと真剣に見つめるべきではないでしょうか。
民間の「顔」を持ったインテリジェンス──その危うさと力
里見甫は軍人ではありませんでした。
彼の肩書は「貿易商」「記者」「文化人」「情報ブローカー」──いずれも民間の顔でした。
しかし、その実態は、
- 満州国を裏から支える資金調達の中心
- 政治工作とプロパガンダの設計者
- 日中関係の水面下交渉の潤滑油
と、まさに“国家の裏方”として働いた人物でした。
民間という立場だからこそ、動ける範囲も広く、責任の所在も曖昧になる。
それが、国家と個人の危うい関係を際立たせています。
今、私たちが学ぶべきもの
現代もまた、国家、企業、個人が複雑に絡み合い、
情報・経済・信念が交差する時代です。
そんな中で私たちは──
- 「誰が実際に動かしているのか」
- 「正義と現実のどちらを取るべきか」
- 「表の言葉の裏にある本音」
といった問いに、目をそらすことはできません。
里見甫の生涯を知ることは、単なる歴史の追体験ではなく、
現代社会の“構造”を理解するための手がかりになります。
里見甫という男の名を、知らずに生きていくことはできる。
だが、彼のような存在が今もどこかで歴史を動かしているかもしれないという事実に、
一度は目を向けてみる価値はあるのではないだろうか。
🧭 里見 甫(さとみ はじめ)略歴
生没年:1896年(明治29年)~1965年(昭和40年)
出身地:福岡県・小倉(現・北九州市)
職業:実業家・政治工作員・情報ブローカー・満州国通信社幹部
🔹 少年時代〜中国との出会い
- 小倉で生まれ、幼少期から柔道に励む。
- 中学生時代、来日中の中国革命家・孫文と接触。日中の国際情勢に関心を持ち始める。
- 柔道大会での活躍をきっかけに中国留学の誘いを受ける。
🔹 中国留学とキャリアの始まり
- 難関の東亜同文書院大学(上海)に福岡市派遣留学生として入学。
- 卒業後、上海の貿易会社に勤務するも、第一次世界大戦後の不況で失業。
- 再び中国に渡り新聞記者に。中国語を自在に操り、中国政財界・軍・裏社会に広く人脈を築く。
🔹 満州事変と政治工作の中枢へ
- 国民党幹部・張学良らと接触し、満州地域の情報・工作活動に関与。
- 張作霖爆殺事件後、関東軍と密接に連携し、情報ブローカーとして台頭。
- 満州国通信社の設立に関わり、プロパガンダ活動・対外広報の中心人物となる。
🔹 アヘン取引と秘密資金ルート
- 満州国の資金源であったアヘンの合法的流通・利権管理に実務責任者として関与。
- アヘンによって得た資金を、軍の機密費や政治工作費に転用。
- 表向きは民間人として行動しながら、国家機構の「裏金ルート」を構築・運用。
🔹 終戦とその後
- 戦後、GHQによる戦犯追及を受けず、不起訴。
- 表舞台から退き、公的には語られることのないまま静かに晩年を過ごす。
- 1965年、死去。
📌 再評価の動き
- 戦後長らく「影の人物」として忘れられていたが、21世紀以降、
満州国史や日本の情報戦研究の中で注目されるようになる。 - 現在は、「戦争を裏で動かした民間人の代表例」として歴史研究の対象に。
🧭 里見 甫(さとみ はじめ)人物相関図
【里見 甫】
|
┌────────┬──────────────┬────────┐
↓ ↓ ↓ ↓
孫 文 東亜同文書院 関東軍 満州国政府
(中学生時代 (留学・中国人脈) (政治工作) (通信社設立)
に接触) (麻薬統制)
|
────────────────
↓ ↓
張学良・張作霖 阿南惟幾(陸軍)・重光葵(外務)
(軍閥・国民党関係) (日本政府の軍事・外交中枢)
|
GHQ
(戦後、戦犯追及されず)
里見甫の年表形式 略歴
| 年 | 年齢 | 出来事 |
|---|---|---|
| 1896年 | 0歳 | 福岡県小倉に生まれる。 |
| 1910年代前半 | 10代 | 中学生時代に来日中の孫文と接触。中国への関心を深める。 |
| 1915年頃 | 19歳 | 上海の東亜同文書院大学に留学。福岡市の推薦による派遣生。 |
| 1919年頃 | 23歳 | 卒業後、貿易会社に就職。第一次世界大戦後の不況で失業。帰国。 |
| 1920年代 | 20代後半 | 再度中国へ。新聞記者・翻訳・通訳業を通じて中国政界と人脈形成。 |
| 1930年頃 | 30代前半 | 満州地域での活動を開始。関東軍と接近し政治工作を担う。 |
| 1932年 | 36歳 | 満州国建国。満州国通信社の設立に関与。宣伝・広報戦略を推進。 |
| 1930年代後半〜 | 40代 | アヘン取引を通じた軍資金調達、諜報活動に実務責任者として関与。 |
| 1945年 | 49歳 | 日本敗戦。里見は戦犯追及を免れ、表舞台から姿を消す。 |
| 1945〜1965年 | 50〜69歳 | 戦後は沈黙を守り、政治的表舞台には一切出ず静かに生涯を終える。 |
| 1965年 | 69歳 | 死去。 |